- 01

- 日本原燃株式会社
- 人財開発グループ
- 平田 詩織さん
- 2023年4月 入職
静岡大学大学院 総合科学技術研究科 理学専攻
物理学コース 修士課程修了

キャリアパスCareer Path
- 2017年3月
- 学校法人静岡理工科大学 星陵高等学校 英数科総合コース 卒業
- 2017年4月
- 静岡大学 理学部物理学科 入学
- 2021年3月
- 同大学卒業
- 2021年4月
- 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 理学専攻 物理コース 入学
- 2023年3月
- 同大学院 修士課程修了
- 2023年4月
- 日本原燃株式会社 入社
- 2023年7月
- 人事部人財開発グループ(現部署)に配属


自然現象を明らかにする知的な冒険―
「物理」への扉を開いてくれた師の存在。
学問において、知的好奇心を刺激し、教え導いてくれる「師」の存在というのは大きなものがあると思います。私は、高校2年の時に担任だった物理の先生の影響で、物理への興味を抱くようになりました。3年に進級して物理の授業以外でも雑談をしたりレクチャーを受けたりしているうちに、「素粒子」に魅了されるようになりました。“これ以上分けることのできない、物質を構成する最小単位”“極微の世界”を学び研究したいと思い、大学は物理学科に進みました。
大学での学修で多様な分野・領域に触れ、新たに興味の対象になったのが「核融合」です。学部4年生から「安全な核エネルギーシステムの実用化」を目標に掲げる大矢恭久研究室に所属し、リチウムセラミックス(核融合反応に必要なトリチウムを生成する材料)、核融合炉の対向材料であるタングステン(プラズマと直接接触する過酷な環境下で使われる高耐熱材)の研究などに取り組みました。
タングステンの研究は、九州大学に設置されている球状トカマク装置 QUESTに試料を装着し、水素プラズマ曝露したものを評価するという研究計画を立てていましたが、折からのコロナ禍(2020年4月、全国対象緊急事態宣言。感染症法上の5類移行は2023年5月)で訪問することができず、試料を郵送し、先方研究者の協力を仰ぐなどの対処が必要でした。
太陽をはじめとする恒星の輝きは、核融合反応により発生するエネルギーによるものです。そのため“地上の太陽”と称される核融合炉は、非常に大きなエネルギーを効率的に生み出し、CO2の排出がない、核分裂反応のように連鎖反応しない、燃料はほぼ無尽蔵…など、たくさんの利点を持っています。私は当該研究からは離れてしまいましたが、多くの工学的課題が解決され、「未来技術」から「実用技術」になることを待ち望んでいます。


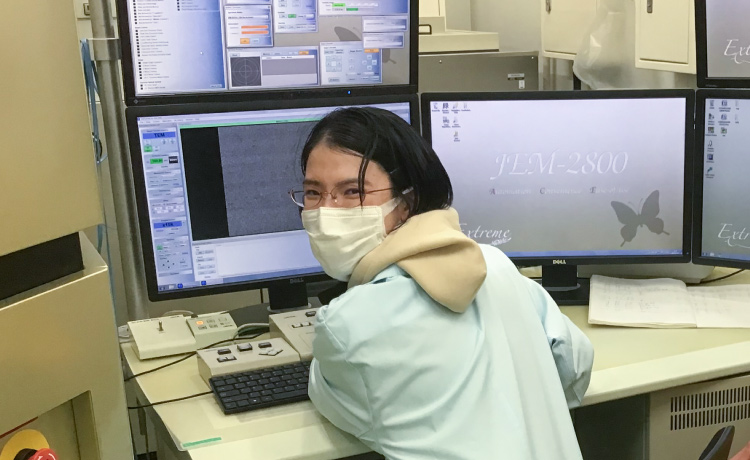

北大での原子力実習、全国から集まった
学生たちとの研究交流も得難い体験。
修士課程2年に在学していた2022年8月、研究室の大矢先生に勧められANEC主催の「北海道大学 電子加速器駆動中性子源を利用した中性子放射化実験・ガンマ線スペクトロメトリーによる元素分析実験実習」に参加しました。内容は初学者にもわかりやすく構成されており、普段、放射線管理実習などの指導助手を務めている私にとっては比較的慣れ親しんだ実験実習でしたが、大学には加速器中性子源が設備されていないので、北海道大学の実機を見られたことは大きな収穫でした。グループワークの課題は中性子の遮蔽実験でした。距離や遮蔽材による減衰(中性子線量率/透過率)を示すグラフが、教科書に掲載されているデータのようには描画されなかったことで盛り上がった記憶があります。また、全国の7大学から学生(学部生から博士課程まで)が集まってきていたので、それぞれの研究テーマや研究室が所有している実験装置などの情報を交換できたことは得難い体験でした。真夏の濃い緑に縁どられる北海道大学札幌キャンパスを散策できたことも良い思い出です。
就職活動に関しては、博士課程への進学を逡巡していたこともあり、少し出遅れてしまったのですが、幸いなことに研究室の行事などで日本原燃(株)を何度か訪れており、会社の業務や社内制度についてお聞きする機会がありました。福利厚生が充実していて働きやすそう、というのがその時に抱いた印象です。仕事で能力を発揮するには、職場環境や支援制度がしっかり整備されていることが必要です。そして、これまで私が培ってきた放射線・放射能に対する知見や知識が生かせるのでは、と考えたことが志望の動機です。
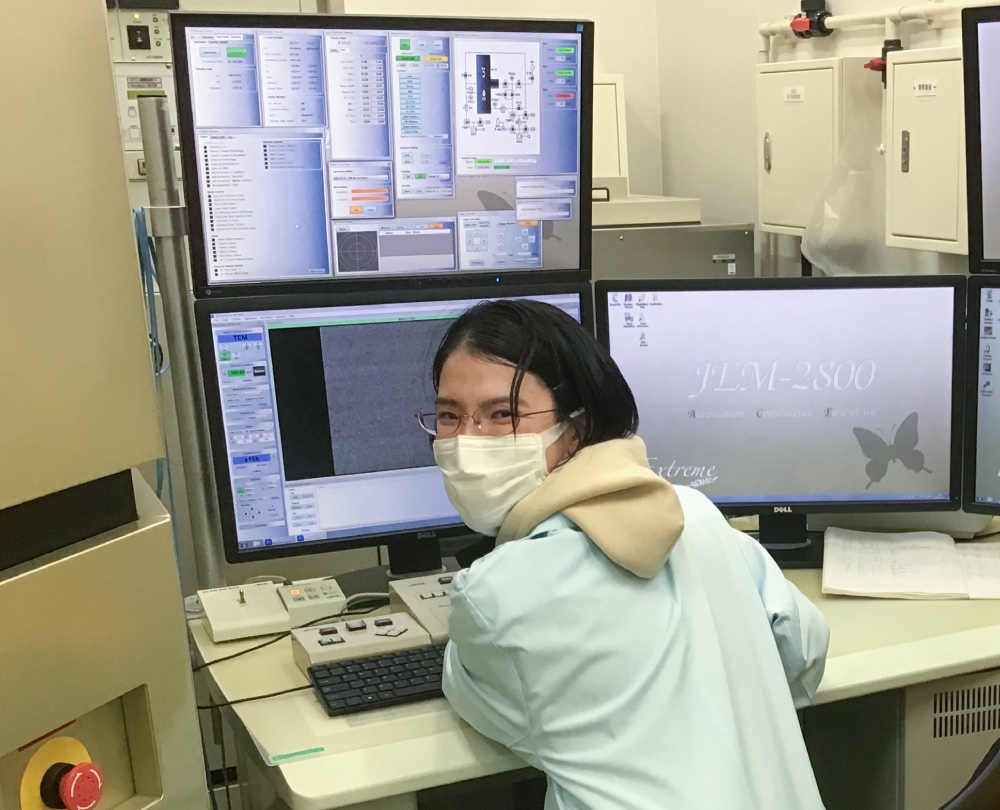


科学的探求や応用研究の土台、専門分野を超えて応用できる
「基礎」を大切に。
現在は、人事部人財開発グループに所属し、新卒採用に向けた業務―会社説明会の企画運営、就職情報サイトの管理、入社試験の連絡、内定者のフォロー、入社式の案内―を担っています。
昨今、新卒人口の減少は続いていますが、大手企業を中心に採用意欲が高く、売り手市場の様相を呈しています。日本原燃(本社)は、遠方に立地(青森県六ヶ所村)しており、抵抗を感じる方も少なくないようですが、そうしたことを補って余りある職務の意義、やりがい、充実感があります。国内では今後、様々な分野での省エネ性能が向上する一方で、気候変動(冷暖房消費)や生成AIの利活用拡大によるエネルギー需要増大のシナリオが見込まれています。2050年カーボンニュートラル達成という大きな目標もあります。そんな中、エネルギー自給率の向上や安定供給、環境問題の解決に貢献する「原子燃料サイクル」を確立するという日本原燃の仕事は、大きな使命と責務を帯びています。
私が経験してきたことを通じて、若い方々に少しお話しできることがあるとすれば、学生時代は「基礎」を大切にしてほしいということです。机上の学びから実験をする段になって、データを解析し、何かの意味を見出し、論文に編むためには基礎的な知識が土台になります。また、大学を卒業、あるいは大学院を修了して社会で働くに際して、自身の専門を100%生かせる道に進むというのは、非常に幸運なことです。畑違いの分野の仕事に就くことも少なくないでしょう。そこでも生きてくるのは専門分野を超えて応用できる基礎知識やスキルです。大木も苗から。基礎をしっかりと養い、知的探究心を存分に育んでほしいと願っています。

会社紹介Company Profile

日本原燃株式会社
- 設立年月日
- 1992年7月1日
- 本社所在地
- 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108
0175-71-2000(代表)
![未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム[ANEC]](https://anec-in.com/cms/wp-content/themes/anec/img/common/anec.svg)

